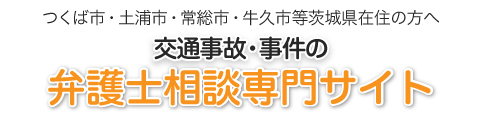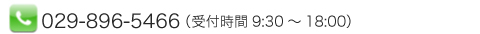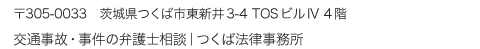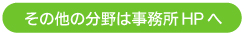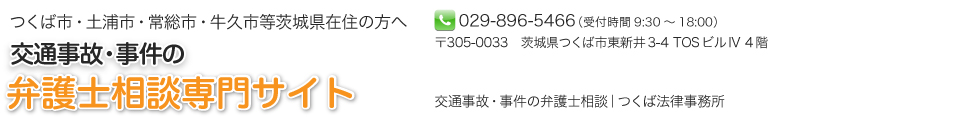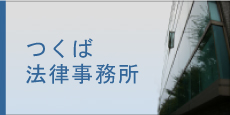交通事故に遭ったら相談を
交通事故で被害に遭われたら弁護士へご相談ください。弁護士に相談することによって、怪我の治療を開始する段階から賠償金の示談交渉を行う段階に至るまで、各段階で依頼者にとって様々なメリットがあります。
特に、後遺障害等級認定の申請や保険会社との損害賠償金の示談交渉は、被害者自身の判断のみで取り組むとなると時間的にも労力的にも負担になるものです。また、被害者自身の判断のみでこれらの申請や交渉を進めた結果、適切な後遺障害等級の認定が得られなかったり、負った損害に相応の賠償金が十分に得られなかったりするなど、不利益を被る事例が多々見られます。
弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級認定を受けられるよう審査に向けた書類作成のアドバイスを提供できることもあり、また、賠償金の示談交渉においても、保険会社から被害者に提示される損害賠償の金額は不当に低く見積もられる傾向にある中、弁護士が示談交渉に介入することで賠償額を増額できる可能性が高くなります。
また、交通事故により精神的な不安を抱える被害者にとって、相談することで不安や疑問等を解消し、今後の一連の流れ・見通しを把握できるなど、経済面のみならず精神面においても、弁護士に相談することによるメリットは大きいと言えます。少しでも疑問が湧いたらその時が相談する時です。たとえ小さな疑問であっても遠慮する必要はありません。気兼ねなくご相談下さい。
相談することのメリット
◇入院・通院時の疑問や困りごとについて相談ができる。
◇後遺障害等級認定の申請を適切に進めることができる。
◇賠償金の示談交渉を有利に進めることができる。
※弁護士が介入することで、保険会社から提示された賠償額よりも増額できる可能性が高まります。
◇精神的なストレスを軽減することができる。
交通事故で想定される問題と相談の例
~事故直後から示談まで~
1.事故直後
これから全般的に何をどうすれば良いのか、全体的な流れを相談したい。
人的損害を被ったにも関わらず、警察で物損事故と処理されているが、どうすれば良いのか。
2.入院・通院
今後の後遺障害等級認定や示談を前提に、入院・通院時の注意点などを相談したい。
治療中にも関わらず、保険会社から治療費の打ち切りの打診がきたが、どのように対応すれば良いのか。
3.症状固定
症状固定後は治療費が支給されないと聞くが、症状固定の時期について医師とどのように相談すれば良いのか。
4.後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級の認定を得たいが、手続きのために何をすれば良いのか。
申請方法には二種類があると聞くが、これらの違いとメリット・デメリットは何なのか。
申請のための書類は何をいつまでに準備して揃えれば良いのか。
症状に見合った適切な等級の認定を得るには、書類に何をどのように記載すれば良いのか。
審査結果に納得がいかないため、異議申し立てを行いたい。
5.示談交渉
どのような項目を損害に含めて賠償金を請求できるのか。
賠償額はどのように算出されるのか。
保険会社から提示された賠償額に納得がいかない。
損害賠償の示談交渉を行いたいが、交渉を有利に進めて相応の賠償金を得るためにはどうすれば良いのか。
示談が決裂したため、調停または訴訟を行いたい。
基礎知識
人身損害の損害賠償
交通事故で怪我を負った場合には、主に次の各々の損害について賠償金を請求できます。
①治療費、入院付添費、通院付添費、
交通費、入院雑費
●治療費とは、治療に必要で尚且つ相当とされる費用です。実費の全額が請求できます。ただし、高額医療、過剰診療と見なされる場合には、適切な治療費と認められないことがあります。高額医療とは、一般に妥当と言える診療費の水準に比して、合理的な理由なく高額であるものを指します。過剰医療とは、診療において医学的に必要性や合理性があるとは言えない余分な医療行為のことを指します。
●入院付添費とは、入院期間に付添人に関わる費用で、怪我の程度や年齢等によって付添人が必要な場合、職業付添人については実費を全額、近親者付添人について相当額が認められます。
●通院付添人とは、通院期間に付添人に関わる費用です。入院付添人と同様に請求できます。
●交通費は、入院や通院に要した費用です。
●入院雑費は、入院期間の必要な日常品など雑費です。
②休業損害
交通事故による受傷から入院や通院をし、勤務先を休まざるを得ない期間分の給与相当額のことです。受傷と交通事故との因果関係があり、尚且つ休業が必要なものであれば、交通事故の前の収入から、休業によって減額した分が認められます。正社員、アルバイトなど雇用形態を問わず、請求することができます。
③入通院慰謝料(傷害慰謝料)
傷害により入院・通院し、その期間に受ける精神的な苦痛について慰謝を求めるための賠償金です。入院期間・通院期間によって支払われます。
④後遺障害による逸失利益
後遺障害が残った場合、障害の程度によって、将来にわたって労働能力の一定割合が失われてしまいます。後遺障害がなければ得られるはずであった収入が、後遺障害によって労働能力に支障を及ぼすがために得られなくなってしまいます。その分の金額を逸失利益として、賠償がなされます。基礎収入に労働能力と労働能力喪失の期間をかけた金額から中間利息を差し引いて算出します。
⑤後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで受ける精神的な苦痛について慰謝するための賠償金です。後遺障害等級に応じて相当額が認められます。
死亡事故の損害賠償
①葬儀関係費用
被害者の葬儀を執り行うに際し支出した費用です。葬儀に加えて、通夜の費用、火葬費、墓石の購入費なども葬儀に関連し必要なものとして認められることがあります。
②死亡逸失利益
存命であれば得られたであろう収入が、死亡により将来にわたって得られなくなります。失われたこの分を死亡逸失利益として、賠償を請求します。基礎収入に労働能力と労働能力喪失期間をかけた金額より中間利息を差し引いて計算しますが、これにもし存命であったならば支出が予想される生活費について一定の割合で控除して算出します。
③死亡慰謝料
被害者が交通事故で死亡したことによる家族の精神的苦痛について慰謝するための賠償金です。裁判所基準の死亡慰謝料は、原則として、一家の支柱が2800万円、配偶者が2500万円、その他の方(高齢者、子供、未婚の男女など)が2000万円~2500万円となります。一家の支柱とは収入によって生計を支えている方のことです。
物損事故の損害賠償
①修理費
修理に要する費用相当額が認められます。
②登録手続関係費等
自動車の買替に際して必要な登録・車庫証明・廃車の法定手数料、ディーラーの手数料報酬の相当額、自動車取得税、および事故車両の自動車重量税の未経過分を請求できます。
③評価損
損傷部位を修理しても、外観上の理由や事故歴などの理由により市場における評価額の低下が考えられれば、損害として相当額が認められることがあります。
④代車使用料
修理期間や買替えの期間に利用するレンタカーなどの使用料です。
⑤休車損
事故車が営業車である場合の、修理期間と買替え期間の損失です。
過失割合、過失相殺
交通事故で被害者側にも不注意などの落ち度がある場合、加害者と被害者双方の落ち度の割合を決め、これが損害賠償額の算出に適用されます。過失割合は、事件に応じて裁判官により判断がなされます。
被害者の損害が500万円である場合、加害者の過失が7割、被害者が3割であれば、請求できる賠償額は350万円と計算します。被害者にも落ち度がある場合に加害者に責任を全て負わせるのではなく、過失の割合を考慮して公平に判断するためのものです。このように過失割合に応じて損害賠償額を決めることを過失相殺と言います。
慰謝料の算定基準
慰謝料とは、被害に遭ったことによる精神的な苦痛に対して賠償をするためのものです。交通事故の損害賠償のうち、慰謝料には入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。これらを算出するための基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3種類があります。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、強制加入保険である自賠責保険による支払いの基準です。人身損害の最低限度を補償するためのものです。
②任意保険基準
任意保険基準とは、任意で加入する保険を販売する保険会社が各社で独自に定めた支払いの基準です。
③裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準(弁護士基準)とは、これまでの交通事故の裁判において慰謝料として認められた金額の裁判例を参考として算出される支払いの基準です。弁護士の介入で交渉や訴訟を行う際に認められる基準です。
これらの3種類の基準には賠償額に開きがあります。自賠責基準では最低限の慰謝料にとどまり、任意保険基準では自賠責基準の慰謝料に各々の保険会社によってある程度を上乗せした金額となりますが、裁判所基準(弁護士基準)では任意保険基準を超える金額を受け取れる可能性があります。
そのため、保険会社から提示された任意保険基準による示談に安易に応じるのは避けましょう。裁判所基準であれば得られるはずの慰謝料に比べて十分ではない可能性を考えておく必要があります。そのため、適正な賠償を受けるには被害者自身で保険会社と示談交渉を行うのではなく、弁護士を入れて交渉を行うようにしましょう。弁護士が保険会社から任意保険基準で提示された賠償額が適正であるか否かを考えることができ、賠償額が不十分である場合には裁判所基準(弁護士基準)に基づいて交渉を進めることができます。
後遺障害等級認定
①後遺障害者等級認定
後遺障害等級認定とは、交通事故後の治療を経て症状固定となったのち後遺障害の内容と程度に応じて、等級の認定を得ることです。等級には14段階あります。
②後遺障害等級認定の重要性
被害者は認定された等級に応じて加害者へ後遺障害慰謝料、逸失利益などの賠償金を請求することができます。後遺障害等級の認定を受けられるか否かで賠償金額の大きさに影響があります。そのため、後遺障害がある場合には等級の認定を受けることが重要となります。
③後遺障害
後遺障害とは、交通事故での受傷により治療を行ってきたものの、これ以上の改善が見込めないがため、症状固定であると医師から判断された時点で残留する症状のことです。
④症状固定
症状固定とは、それまで継続してきた治療をこれ以上行っても、将来にわたって症状が改善しないものと判断された状態のことです。また、症状が固定したと判断がなされた時点を症状固定日と言います。症状固定の判断は医師によって行われるべきものです。ところが、治療を継続中にも関わらず、保険会社から症状固定として治療費の支払いの継続の打ち切って良いかと打診されることがあります。この打診をそのまま受け入れると、それ以降の治療費を受け取れなくなってしまいますので、注意して下さい。
後遺障害等級認定の申請準備と申請方法
①後遺障害診断書の準備
症状固定と判断されたら、医師より後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害等級認定の審査において重要な書類となります。なぜなら後遺障害認定の審査は、医学的な客観性を重視する書類審査であるためです。適切な後遺障害等級の認定を得るには、後遺障害診断書を作成してもらうに当たって、等級の認定に必要な検査内容と残存する自覚症状と後遺症の程度とを不足することなく記述に反映してもらえるようにしなければなりません。
②後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定を受けるための申請方法には、加害者側の保険会社による事前認定と、被害者による請求者請求の二通りがあります。
事前認定とは、加害者側の保険会社が申請の手続きを行うものです。被害者側で手続きを行う必要がない分、手間がかからない方法ではありますが、被害者にとって有利な医証の提出ができないのが欠点です。また、自賠責保険の保険金の支払いが遅れます。
被害者請求では、被害者が自ら申請の手続きを行うものです。申請に必要な書類を被害者自身で揃えて用意する必要があります。しかし被害者にとって有利な医証の提出ができるとともに、自賠責保険の保険金が早期に支払われるという長所があります。
③被害者請求の手続きに必要な書類
被害者請求ではその手続きにあたって、支払い請求書、請求者本人の印鑑証明、交通事故証明書、事故発生状況報告書など書類が必要になります。
異議申立て
後遺障害等級認定の申請と審査後、等級が非該当とされ認定そのものを受けられなかった場合や、等級の認定は得られたものの望んでいた等級よりも低い等級で認定されてしまった場合には、異議申立てを行うことができます。異議申立てを行える回数に制限は設けられていません。ただし、認定の内容を覆すには認定の誤りを証明するための医学的・客観的な証拠を提出する必要があります。