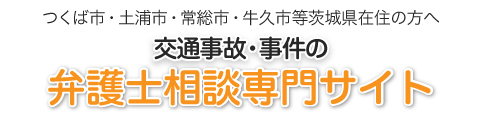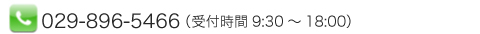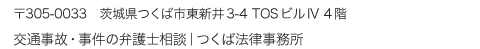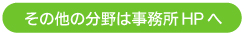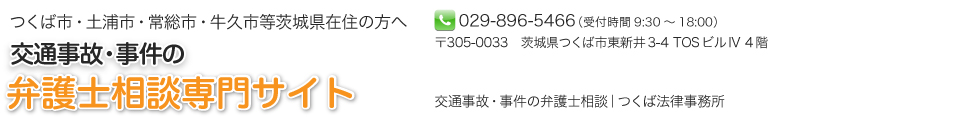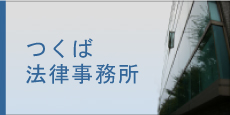1. 相談のご予約
ご相談は全て予約をしていただいたうえで行います。
予約方法
お電話(029-896-5466)か、お問い合わせフォームから相談のご予約をお願いいたします。
お問い合わせの際には簡単にご相談内容の確認をさせていただきます。
業務時間
平日9:30~20:00 定休日:土日祝日
平日ご勤務の方のため、平日午後6時以降にご相談日時を設けることも可能です。
また、ご事情に応じて、定休日や早朝・深夜等の業務時間外に相談予約を入れることも検討いたします。事前にお問い合わせください。
2. 料金について
◇弁護士費用特約のある方は無料相談可能です。
◇その他の場合の法律相談は、30分5,500円(以降10分超過毎に1,832円。)です。
◇法律相談のための調査に要する時間も法律相談時間に含みます。
◇出張法律相談可。出張法律相談は全て有料です。1時間毎に11,000円(移動時間含む。)。
◇電話、オンライン法律相談は全て有料です。30分5,500円。
3. 法律相談
抱えている問題についてお話をうかがい、法的な見通しを示し、助言を行います。
また、ご相談内容から、事件受任の必要・可否を判断します。相談のみで事件を依頼しなくとも構いません。
来所相談
面談による相談は原則として、当事務所で行っております。ただし、入院中・通院中で身体が不自由などの事情がある場合は、他の場所で相談することを検討することもあります。
電話、オンライン法律相談
1、当事務所宛にご予約のご連絡(電話、メール、問い合わせフォームをご利用ください。)をしていただきます。
2、当事務所からお電話で簡単に事案の聞き取りをいたします。
3、聞き取りの結果、法律相談可能な場合は、当事務所の法律相談料の振込口座をお教えします。
4、期限までに、お教えした振込口座に30分の法律相談料5500円をお振込みいただきます。
5、お振込み後にお電話をお願いします。その際、法律相談日時を決めます。
6、お電話またはオンライン(Zoomによるビデオ通話)による法律相談を30分間行います(原則として延長不可。別途予約を取って再相談をすることは可能です。)。
7、事件についての依頼をご希望される場合は、当事務所にお越しいただき、受任契約書を交わした後で、お引き受けいたします。ただし、入院により来所が困難な場合は病院等、他の場所を検討することもあります。
なお、法律相談の結果、ご相談者様が依頼を希望されても、事件受任をすることができない場合がありますので、その点については、あらかじめご了解ください。
相談時間
ご相談の多くは、30分~1時間程度で終了します。もちろん、事案が複雑な場合は1時間以上の時間が必要となることもあります。
事前準備
ご相談の際は、交通事故に遭われた後の現在の状況(怪我の診断内容、入院・通院の状況、後遺障害等級認定申請の状況、賠償金請求の状況等)を中心にうかがいます。
現在の状況に応じて関係あると思しき資料(入院・通院の際の診断書、後遺障害等級認定の通知書、保険会社からの示談書等)をご提示いただけると助かります。
資料等をご持参またはメールでいただければ、スムーズに法律相談を行うことができます。
4. 方針決定・契約
相談のみで終了しご契約いただかなくとも構いませんし、一旦持ち帰ってご検討いただき、後日ご依頼をいただくことも可能です。
解決までの流れ
①事故直後
警察への通報、人身事故の届け出、加害者情報の確認、保険会社への連絡を行ってください。
▽通報と人身事故の届け出
通報することで警察から交通事故証明書が発行されます。これは損害賠償請求の際に必要となる書類です。また、現場で警察に人身事故として届け出て下さい。人身損害の賠償を請求するには、人身事故として処理されている必要があるためです。怪我を負ったにも関わらず物損事故で処理されていた場合には警察署で人身事故への切替えの手続きを行ってください。
▽加害者情報の確認
加害者に関する情報を事故現場で確認して記録して下さい。氏名、住所、連絡先、自賠責保険と任意保険の情報、車のナンバーなどです。
▽保険会社への連絡
加入する保険会社に連絡してください。
②治療(受診、入院、通院)
病院で診察を受け、症状を不足なく伝え、必要な検査を受けて下さい。また、入院、通院は医師により治療の終了の判断がなされるまで継続してください。この間の治療費は加害者側の保険会社に請求します。
▽受診
自覚症状が小さかったり無かったりしても、気付かない所に損傷が内在していて後に症状が出現することもありますので、交通事故に遭ったらすぐに受診して検査を受けてください。また、事故から受診までに長い期間を置くことは、後遺障害等級認定の申請や損害賠償請求おいて事故との因果関係を証明する上でも不利になりかねません。
▽入院・通院
受診後は入院・通院等の治療と検査を継続して受けてください。通院は、必要な頻度で通院し、次の通院までの間隔を開け過ぎないよう注意してください。治療費を受け続けられるためにも、また適切な後遺障害等級認定を受けるためにも大切なことです。
③症状固定
症状固定の時期は医師に判断してもらいます。治療中に保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けた場合でも、症状固定の確定については医師の判断を重視して下さい。
▽症状固定の判断
症状固定とはこれ以上治療を継続しても改善が見込まれない状態のことを言います。一旦、症状固定が決まるとその後は保険会社から治療費を受けられませんので、症状固定の時期の判断は医師により慎重になされなければなりません。
▽治療費打ち切りの打診
症状固定前であるにも関わらず保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けることがあります。入院・通院等の治療中であれば安易にこれに同意することなく、治療を継続中である旨を保険会社に伝えて下さい。
④後遺障害等級認定
症状固定後に医師から後遺障害診断書を受け取り、後遺障害等級認定の申請を行います。認定機関による審査を経て等級の認定がなされます。等級には14段階があり、後遺障害の内容と程度に応じて等級が決まります。
▽後遺障害等級認定の重要性
後遺障害等級認定を受けることで、のちの損害賠償請求において後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益の請求を行うことが可能となります。そのため、後遺障害に見合った適切な等級認定を受けることが重要になります。
▽事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定の申請方法には事前認定と被害者請求があります。事前認定は加害者側の保険会社に申請を一任するものです。被害者請求は被害者側で書類を揃えて申請するものです。被害者請求では申請書類の記述内容や申請の過程を被害者側で把握できることが利点です。
▽異議申し立て
等級が非該当とされた場合や認定された等級に不満がある場合には、異議申立てができます。
⑤示談交渉
保険会社から提示される損害賠償額は低く見積もられ、十分な補償が受けられるとは言えません。弁護士が示談交渉を行うことにより、受け取れる賠償金の増額が期待できます。示談交渉では、休業損害の範囲、逸失利益に関わる労働能力喪失率、過失割合、交通事故と後遺障害の因果関係、その他数々の争点について保険会社と話し合います。
▽損害賠償額の算定基準
算定基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3種類があります。保険会社が設定する任意保険基準による提示額は、自賠責保険基準に少々上乗せした程度である場合が多く、弁護士が示談交渉に介入し弁護士基準(裁判所基準)による賠償額の支払いを求めることで、より有利な賠償金を受け取ることができます。弁護士基準(裁判所基準)とは、これまでの交通事故事件の裁判において認められた例を基にして額を算出するものです。
▽請求できる損害賠償
被った損害の内容と程度に応じて損害賠償を請求できます。請求できる損害は主に次の通りです。
| 人身損害事故の損害賠償 |
|---|
|
・治療費・入院付添費・通院付添費・入院雑費 ・休業損害 ・入通院慰謝料(傷害慰謝料) ・後遺障害による逸失利益 ・後遺障害慰謝料 |
| 死亡事故の損害賠償 |
|
・葬儀関係費用 ・死亡逸失利益 ・死亡慰謝料 |
| 物損事故の損害賠償 |
|
・修理費 ・登録手続関係費等 ・評価損 ・代車使用料 ・休車損 ※物損事故では慰謝料は請求できません。 |
▽過失割合と過失相殺
交通事故で被害者側にも不注意などの落ち度がある場合、加害者と被害者双方の過失の割合を損害賠償額の算出に適用します。例えば、被害者の損害が500万円である場合、加害者の過失が7割、被害者の過失が3割であれば、請求できる賠償額は350万円と計算します。このように過失割合に応じて公平に損害賠償額を算定することを過失相殺と言います。
⑥民事裁判提起
保険会社と示談交渉が決裂した場合には、交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センター等に仲裁を求めたり裁判所へ民事調停を申し入れたりすることもできますが、最終的な解決方法は民事訴訟です。訴訟では、弁護士基準(裁判所基準)で損害賠償額が算出されます。通常、訴訟の提起から判決までに半年~1年半ほどですが、争点の多さや複雑さ次第ではそれ以上の期間を要することもあります。
⑦裁判の流れ
| 民事裁判訴訟の提起 |
|---|
| 原告(被害者)は、主張を裏付ける証拠資料と併せて訴状を裁判所へ提出します。 |
| 期日指定と被告答弁書の提出 |
| 裁判所が第一回口頭弁論期日を指定し、原告・被告に通知します。被告は訴状に反論する答弁書を裁判所へ提出します。 |
| 口頭弁論期日 |
| 公開法廷において、原告・被告の双方が主張・立証を述べる口頭弁論期日が開かれます。また、争点の整理を行うために非公開で争点整理期日が行われることがあります。 |
| 和解 |
| 裁判中に和解が提案されることがあります。被害者と加害者の双方が和解案に合意すれば、判決を待たずこれをもって裁判の終了となります。 |
| 尋問期日 |
| 和解が成立せずに訴訟が進んだ場合、公開の法廷で、証人や事故の当事者本人の尋問を行うことになります。尋問終了後、当事者本人双方が出廷していることから、尋問の結果を踏まえた和解の協議が行われることがあります。 |
| 判決 |
| 和解が成立しない場合は、判決が言い渡されます。判決に不服の場合には控訴、上告ができます。 |
⑧損害賠償金の受け取り
示談交渉での示談成立したのち、または仲裁・調停や民事訴訟での和解成立・判決ののち、保険会社から損害賠償金が支払われます。